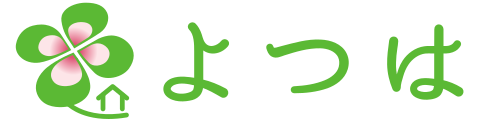三方よし
・働き手が満足する環境を作っていく(働き手よし)
・利用者様が満足するサービスを提供していく(ご利用者様よし)
・社会が必要とするものを生み出し、社会の発展に寄与する(社会よし)
『売り手によし、買い手によし、世間によし』を示す『三方よし』という表現は、近江商人の経営理念を表現するために後世に作られたものですが、そのルーツは初代伊藤忠兵衛が近江商人の先達に対する尊敬の思いを込めて発した『商売は菩薩の業、商売道の尊さは、売り買い何れをも益し、世の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの』という言葉にあると考えられています。
自らの利益のみを追求することをよしとせず、社会の幸せを願う「三方よし」の精神をもって、日々の仕事に社会、コミュニティ、個人のニーズを満たすためにはチームを目指します。
虚往実帰
・行きは不安で虚しい気持ちであっても、帰りは満ち足りていく環境を作る
『虚往実帰(きょおうじっき)』とは、弘法大師空海が「荘子」から引用したと言われている言葉です。この意味には、『師などから無形の感化や徳化を受けるたとえ』とあります。つまり、行くときは何も分からずに空っぽの心であっても、帰るときには師の教えによって充実して、十分に満足しているということです。もともとこの言葉には、遣唐使として唐に渡り様々な知識を日本に持ち帰ってきた空海自身の感慨が込められています。
もちろん、私たちは『師』ではありません。ご利用者様から多くのことを学ぶことがあります。我々はこの『師』という意味合いを取り除き、『働き手もご利用者様もともに無形の感化や徳化を受けられる事業にしたい』という思いを持っています。
働き手も新しいご利用者様と接するときには不安もあります。でも、ご利用者様に良かったと言われれば、とても満たされた気持ちになります。当然、ご利用者様も同じ事だと思います。初めての場所で初めての人に自分の体を預けるのに不安がないはずがありません。だからこそ、不安な気持ちで来られた方に、来て良かったと言ってもらえるサービスを提供していきます。